学科試験
試験を受ける準備ができたら運転免許試験場に行きます。

受付時間
月曜日〜金曜日(土日祝日・振替休日・12月29日〜1月3日を除く)、8時45分〜12時
持ち物
- 本籍が記載された住民票
- 本人確認書類(健康保険証やマイナンバーカード、パスポートなど)
- 仮運転免許証
- 証明写真2枚(6ヶ月以内に撮影した帽子なし、正面、無背景のもの)、サイズは縦3cm×横2.4cm
- 手数料2,550円(受験手数料)
- 黒色ボールペン
- 運転にメガネが必要な方はメガネ(視力検査があります)
学科試験の流れ
- 11番窓口で証紙を購入
- 13番で受験の受付
- 適性検査(視力検査)
- 4階試験室で学科試験
- 2階のディスプレイ掲示板にて合格発表
- 合格発表の際のアナウンスで言われた窓口に行く(合否で行く窓口が違う)
- (合格の場合)技能試験の日時が指定された用紙をもらう
- (不合格の場合)今回の試験の点数が記載された用紙をもらう
この日は、受付時間前の8時30分頃に運転免許試験場に到着しましたが、既に11番窓口には長蛇の列が・・・。
学科試験は、午前中に2回、午後に1回行われます。
「受付開始時間前から並んでるから遅くても2回目には受けられるだろう」と思っていましたが、何故か途中で全然列が進まなくなり、結局3時間近く並んでやっと11番窓口の受付に辿り着くことができました。
お昼ご飯
試験が午後からになったので、お昼ご飯をどうしようかと思いました。
試験場内にも2階に定食屋さんがあり、そこにはパンなどの軽食も売っています。また、試験場のすぐ近くにコメダ珈琲もあります。
私は、試験場内の定食屋さんでお昼ご飯を食べて、4階の試験場前のベンチで試験時間まで過ごしました。

学科試験開始!
時間になり、試験会場に入り、合図とともに試験開始です!
・・・・・。勉強したことと、全然違う問題だ・・・。

と、いうことで1度目の試験は落ちてしまい、別日に再度受けて合格しました。
学科試験に合格すると、技能試験の日時が指定された用紙を渡されます。本当は、ここで技能試験のコースが記載された地図を渡されるらしいのですが、私はむこうの方が忘れていたらしく貰っていませんでした。
後日、平針自動車練習場で運転練習した際に指導員の方から「もらった地図で試験ルートをなるべく覚えた方が良いよ」と言われ「地図をもらってないんですけど、どこでもらえるんですか?」というやり取りがあり、渡されていないことが判明しました。
実技試験の日時が指定された用紙をもらったときに地図が渡されなかったら、窓口で問い合わせてみてください。
技能試験
学科試験合格の際に指定された日時に平針の愛知県運転免許試験場に行きます。

持ち物
- 受験票
- 運転免許申請書及び運転免許試験等結果通知書
- 仮運転免許証
- 試験車使用料880円(2回目からは受験手数料2,550円が追加される)※普通車の場合
- 運転にメガネが必要な方はメガネ
技能試験の流れ
初回は、受験手数料が控除となりますが、試験車使用料は必要になるので、最初に11番窓口に並びます。
- 11番窓口で試験車使用料を払う
- 17番窓口で技能試験の手続き
- 試験(路上コースと試験場内で縦列駐車もしくは方向転換)
- 2階のディスプレイ掲示板にて合格発表
- 合格発表の際のアナウンスで言われた窓口に行く(合否で行く窓口が違う)
- (合格の場合)4階の窓口で今後の説明を受ける
- (不合格の場合)再度指定された日時が記載された紙をもらう
技能試験開始!
集合時間の少し前になったら17番窓口で手続きの際に伝えられた場所に行きます。
時間になると試験の方が来て名前などの確認をされます。このときに試験管の方から「試験のルートは知っていますか?」と聞かれたので「知りません」と答えたところ「試験中に隣で道順を説明するので大丈夫ですよ」と言っていただいて安心しました。
数年前まで技能試験は試験ルートを暗記しなくてはならなかったらしく、受験者は自分で覚えた道を運転しなくてはならなかったそうです。
平針が地元の人は良いかもしれませんが、全然違う場所に住んでいたら運転したことのない土地の道順を覚えるのってとても大変だと思います。
もし、今もルートを覚える試験方法だったら私の合格はいつになっていたか分かりません。
試験は、私ともう1人の受験者の方で車に乗り、途中で運転を交代しました。
平針自動車練習場で指導員の方から聞いたポイントに気をつけながら運転をして、見事技能試験は1回で合格することができました!

合格しても直接受験者は当日免許発行されません!
技能試験に合格したら4階の窓口で今後の説明を受けます。
免許をもらうには「取得時講習」と「応急救護処置」の講習を受けてから、再度試験場に来なければなりません。
自動車学校に行った人たちは学校で講習を既に受けているため、試験場で学科試験に合格すれば運転免許が交付されますが、直接受験者はそうはいかないのです!
2つの講習は、4階の窓口でもらった「講習を実施している自動車学校一覧表」に記載されている自動車学校に自分で電話をして予約を取るのですが、これが何箇所かかけても「うちでは受付していません」と言われ(だったら一覧表に載せないでよ!)、私は7箇所くらい電話してやっと予約できました。
また、この講習は自動車学校によって2日に分けて行うところと1日で行うところがあります。私は別のことで有給休暇が使いたいため、1日で終わるところを予約しました。
取得時講習と応急救護処置
取得時講習は指導員の方に運転をみてもらいアドバイスをいただいたり、授業形式でお話を聞いたりします。
応急救護処置は、人形相手にAEDの使い方と心臓マッサージを学びます。
講習時間は朝9時〜16時くらいまで丸1日かけて行われます。
講習料金
取得時講習 手数料 11,200円
応急救護処置講習 手数料 4,200円
合計 15,400円
やっと免許交付
取得時講習と応急後処置の修了証を持って愛知県運転免許試験場に行きます。
ちなみに取得時と応急処置の講習から1年以内に免許交付の手続きをしないと、再度講習を受けなければならないそうなので、気をつけてくださいね。
11番で交付手数料2,050円を支払い、4階の写真撮影をしている部屋に行ってスタッフの方に直接受験で取得時講習を終えてきた旨を伝えます。
そうして写真撮影の後、念願の免許が交付されます。
全てを終えて
私は仕事をあまり連続で休むと自分の仕事量的に厳しかったこともあり、急いで再取得を目指していなかったこともあり、運転免許失効から再取得まで6ヶ月かかりました。
そして5日間有給を使い、お金はトータルで5万円くらいかかりました。
自動車学校に行くことを思うと金額的には大分安くすみましたが、毎年誕生日近くになったら気にして免許証の有効期限を確認していれば必要のなかったお金です。
仕事で車を使う方は運転免許がないと本当に困ると思いますし、私のように仕事では使わなくても1人でスーパーで買い込んだときに自転車のカゴに荷物を乗せて帰るのは大変でした。
本当はスーパーに行った後にドラッグストアでティッシュやトイレットペーパーが買いたくても、自転車のカゴに全部は乗らないから今日はやめておこうと思った日もあったので、やっぱり車があると便利だなと思いました。
今、もしあなたがうっかり失効したことに気付いて再取得に向けて取り組んでいる最中でしたら、今はとても不安な気持ちかもしれません。
私は、失効に気付いた日は落ち込みと不安な気持ちでいっぱいでした。
しかし、一つひとつをしっかりこなしていけば、また数ヶ月後には車を運転できると思いますので、焦らずに頑張ってくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

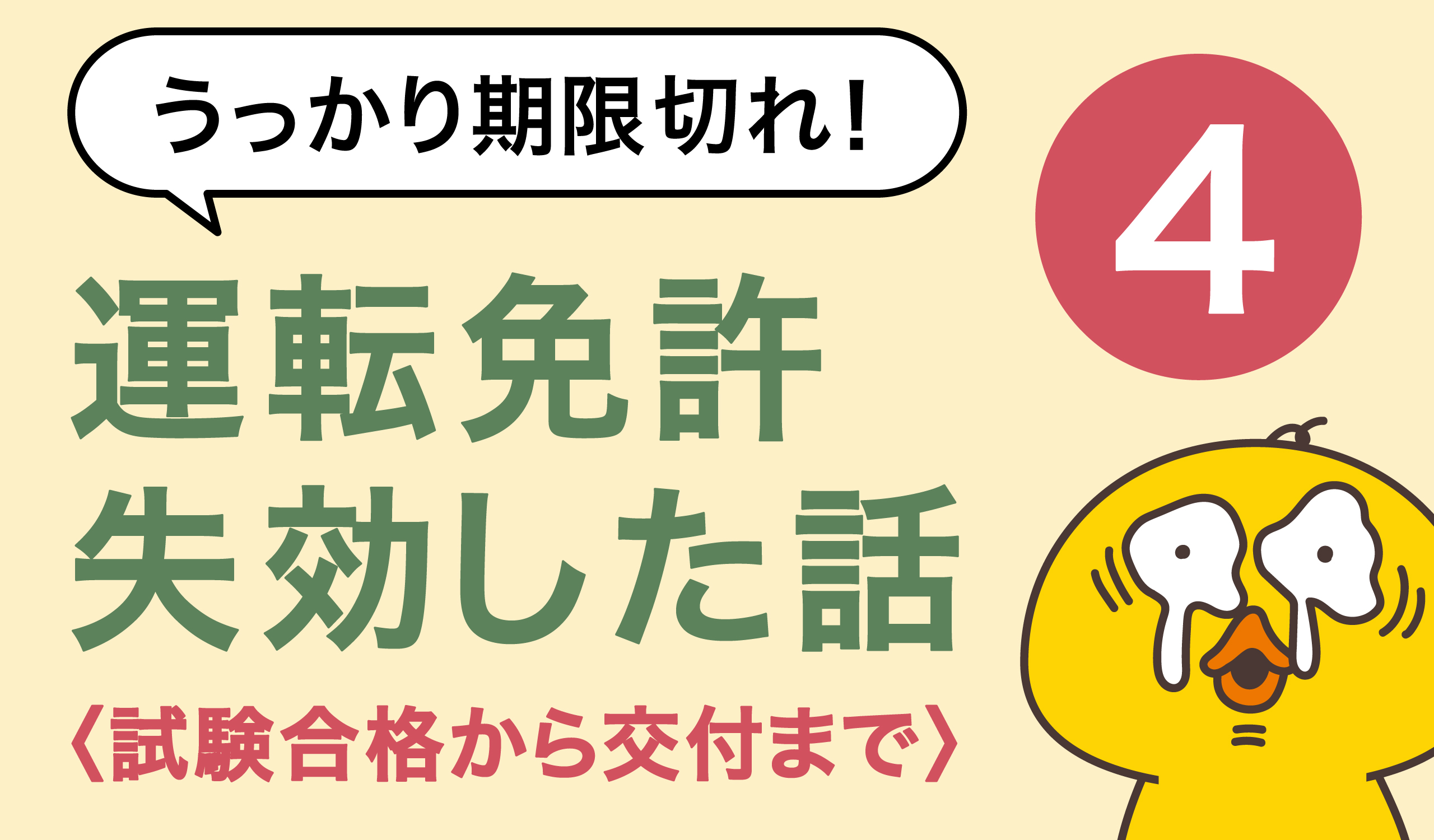

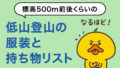
コメント